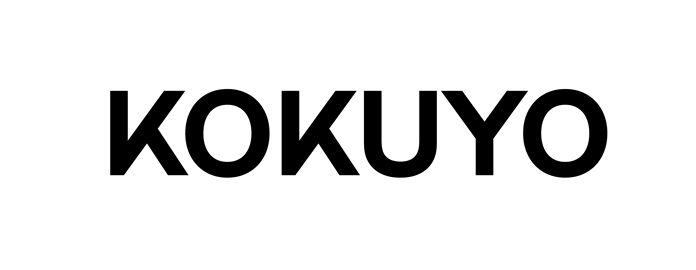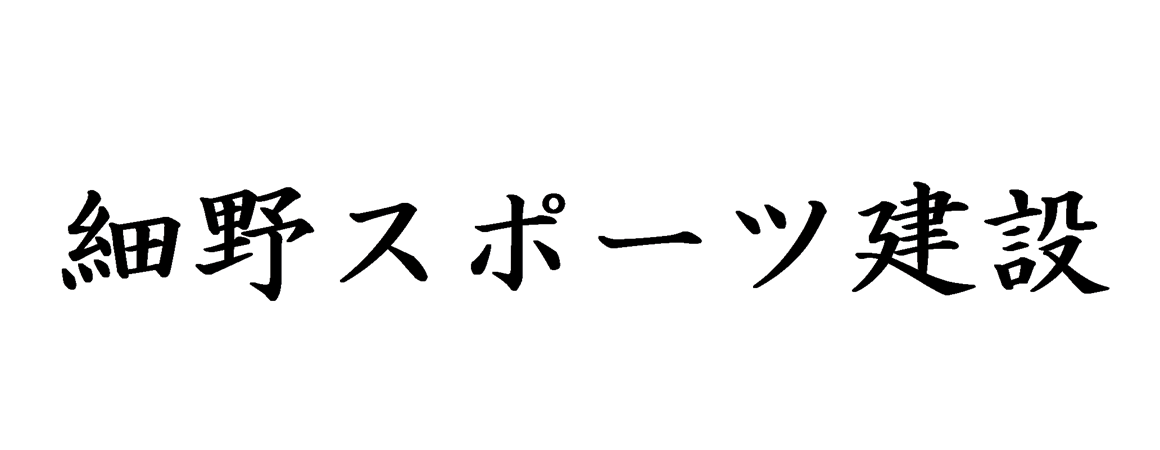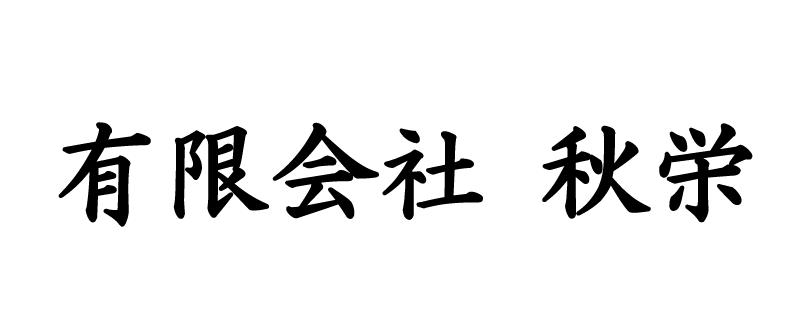【道標 Vol.8】品川 英貴

幸せな仕事に就いている。
故郷で母校ラグビー部の監督を務めて16年。その間に長崎北陽台高校を11回も花園に導いている。
同校の品川英貴(ひでたか)監督は、府中のグラウンドでラグビーマンとして8年間汗を流し、会社員として働いた人。国立競技場も駆けて、日本一の栄冠も手にした。
167センチの身長ながら、キレのある動きと広い視野を持つスタンドオフだった。日体大から当時日本選手権を連覇していたチームに加わった。1998年の春だった。
チームを率いていた向井昭吾監督の誘いを覚えている。
「いちばんダメな誘い方でしたよ」と笑い、続ける。
「お前が本当に来たいんだったらいいぞ。ただ、甘い世界じゃないからな、と。うちはポジションをあけて待っているよ、というチームも他にあった中で、その言葉がグサッときました」
心は決まった。
チームは自身のルーキーイヤーに日本選手権3連覇を果たすも、その後、低迷する。
しかしトップリーグが始まった2003年に再浮上した。同年の日本選手権では決勝で神戸製鋼を22-10と破り、日本一となった。
品川さんはその試合で輝いた。途中出場でピッチに立ち、14-10と競っていた後半37分。相手ディフェンスのギャップを突破し、勝負を決めるトライを奪った。
「優勝の瞬間、グラウンドに立っていられる感覚は格別でした。見たことのない景色を国立競技場で見させてもらった。いい思い出です」

在籍した8年は曲がりくねった道だった。
反則を得たらタップキックを号砲にすぐ攻める。「PからGO」と名付けられたアグレッシブさで国内シーンを席巻しているチームに入った。
しかし、沈み、もがいたシーズンもあった。そんな時間を経て、自分の活躍もあり、日本一に返り咲いた。
そんな日々を振り返って、「ラグビー選手として、そして社会人としても、人間の幅を広げてもらった期間」と、様々な経験と感動を与えてくれた環境に感謝する。
薫田真広監督が率いたチームでは、フォワードやバックスに関係なく、いろんなポジションの選手たちが一緒に体をぶつけ合うモールゲームが名物練習だった。
品川さんは東芝に入って、ラグビーの原点を体感した。
ラグビーは格闘技の要素も強い。フィジカルの強さこそ、勝負どころ、修羅場で相手との差が出る。その信念のもと猛練習を重ね、実際の試合では大事な時間帯を制した。
「強い、と言われるより、相手に『東芝と戦うと痛い』と言われることを喜ぶチームでした」と懐かしむ。
チームメートは猛者揃いだった。負けじ魂がぶつかり合う部内マッチの激しかったこと。「AとBの2チームで大会に出れば、決勝で両チームが戦うことになるのでは、と思うほどの本気度でバチバチやっていました」。
「夏合宿での部内戦は激しすぎて、このまま続けたら喧嘩になるから、と途中で打ち切りになったこともありました。(CTB新里)二郎さんとか、本当に熱かった」
そういった時間も含め、練習でやったことが試合に出るのだと、あらためて実感した。
それだけ本気でぶつかり合ったからこそ、結束の強い集団だった。
「私は東芝でしかプレーしていませんから他のチームのことは分かりませんが、間違いなく部員同士の結びつきはどこよりも強かったと思います。ファミリー感はいちばんと自信がある」
チームカルチャーは、グラウンドやクラブハウスだけでなく、宴席でも先輩から後輩へと伝えられた。
「それぞれが別のところで飲んでいても、最後には府中に戻ってきて、みんなで集まってまた飲む、というチームでした」

8年間の府中生活の間に得た財産は、いま、長崎で指導者として高校生たちと向き合うときに生かされている。
一人ひとりのラグビー人生は高校を卒業しても続く。だから、どんなカラーのチームでもやっていけるように、基本プレーを徹底して伝える。
「いまの時代、その気があれば海外ラグビーの映像などにいくらでも触れられるし、それによって一人ひとりにいろんなイメージが湧くでしょう。でも、やはりしっかりした土台は持っていてほしい」
フィジカルの強さを持とう。ディフェンスにこだわろう。そう呼びかけ、チームの根幹を作る。
「東芝もそうだったように、勝ち続けるんだ、というプライドを持つことは大事。そして、ディフェンスがうまくいけばアタックもうまくいくようになる」
その感覚を「勝手に思っていること」と言うけれど、プレーヤーとしても、指導者になってからも、実際に体感して得た真実。だから鮮やかなブルーのジャージーは、いつも全国大会の舞台に立ち、必ず爪痕を残す。
2023-24シーズンに見せたブレイブルーパスの頂点への躍動は、家族と共にテレビを見て楽しみ、叫んでいたと笑う。
同じポジションの経験者としてリッチー・モウンガが周囲に与える影響の大きさはよく分かる。しかし、チームには何人もハードワーカーがいて、昔と変わらず体をぶつけていくスタイルがあった。それこそが優勝の下地にあると感じられたのが嬉しかった。
春の全国選抜大会で熊谷へ、夏の全国セブンズ大会で菅平へチームとともに遠征したとき、必ず応援に来てくれる人がいる。
職場で隣のデスクに座り、いつもラグビー部を応援してくれていた方とは、いまもそんな形で交流が続いている。
自分の懐かしい日々を覚えてくれている人が、どこかにいる人生っていい。職場で、ピッチで、いつも全力だった。そんな姿は、必ず誰かが見ていてくれる。
教え子たちにも、そういう生き方をしてほしい。
(文中敬称略)
(ライター:田村 一博)

【連載企画】東芝ブレイブルーパス東京 「道標」
・「道標」一覧はこちら




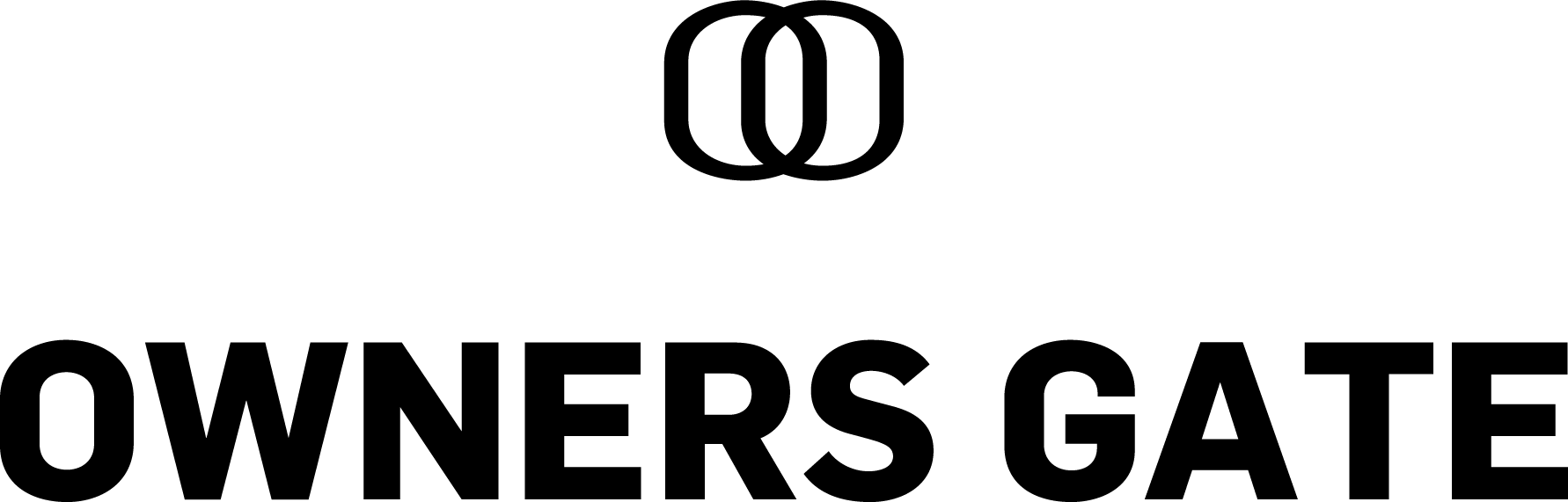




















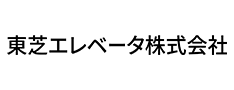



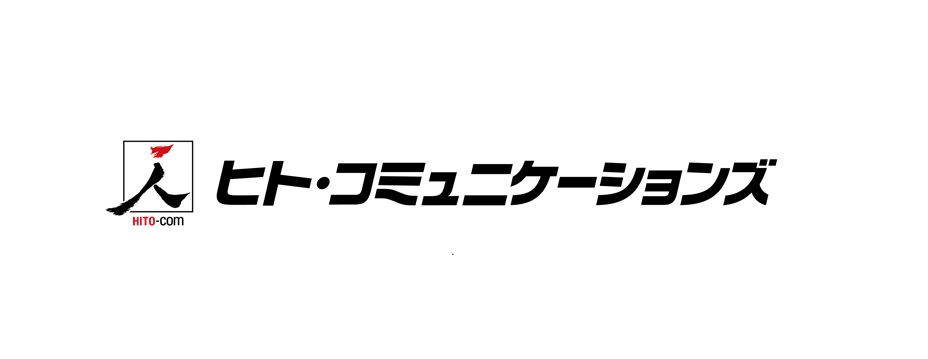

















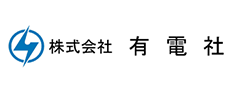


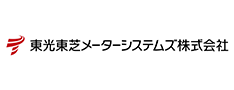
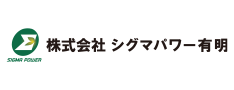

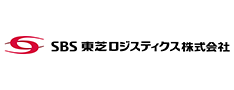




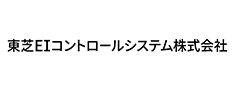

.jpg)


レスター.png)
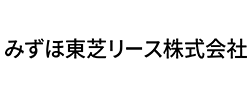
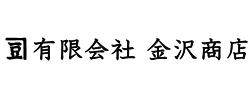
-07.jpg)


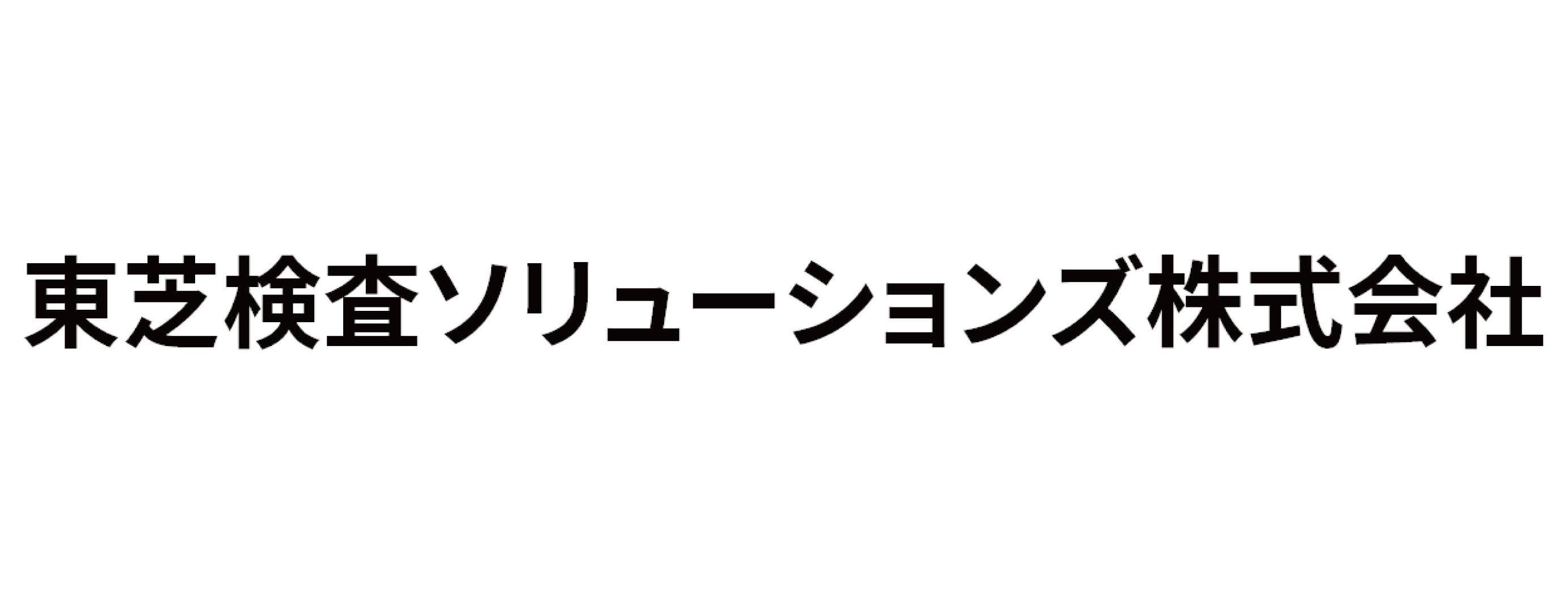





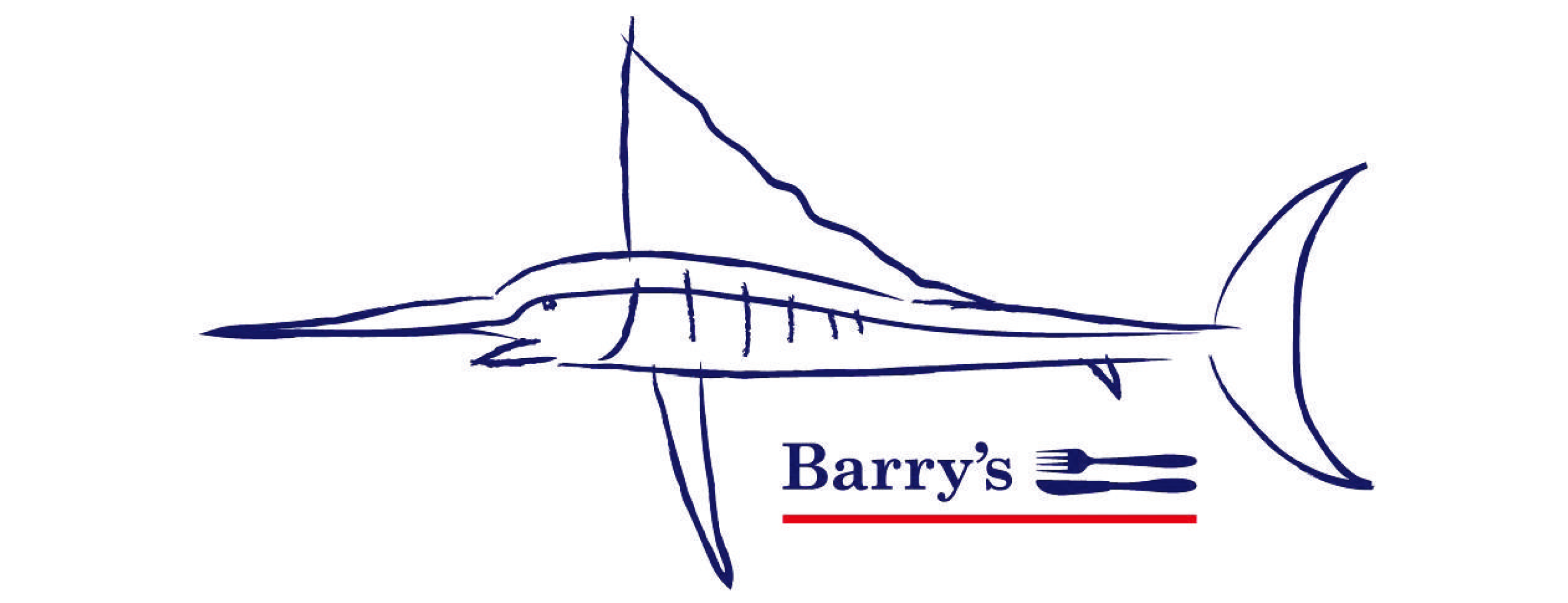

日本計装.jpg)


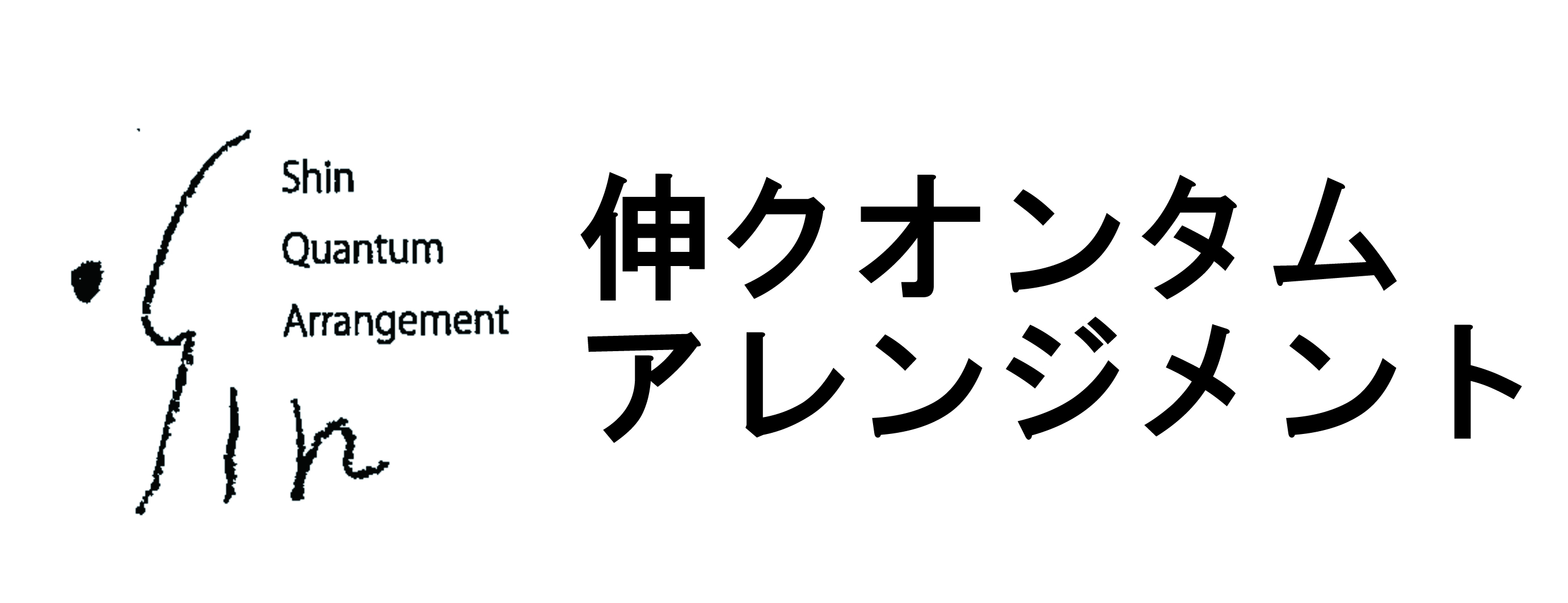
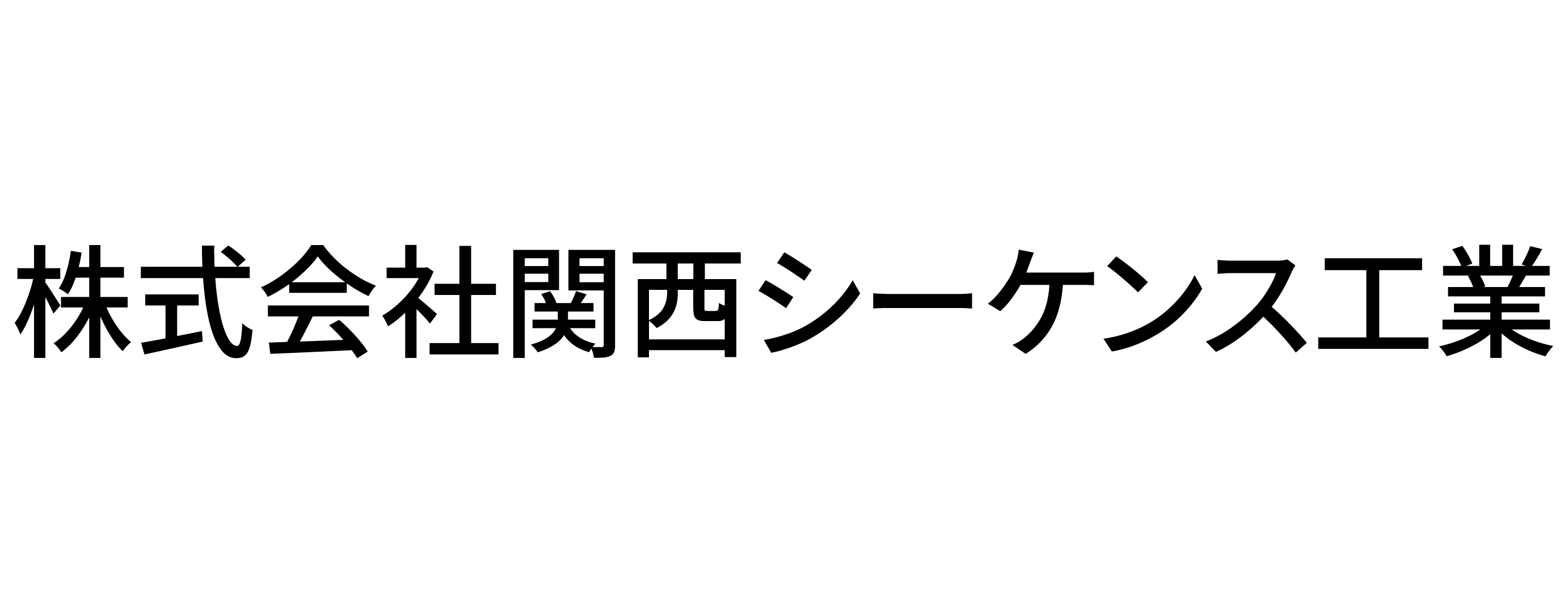
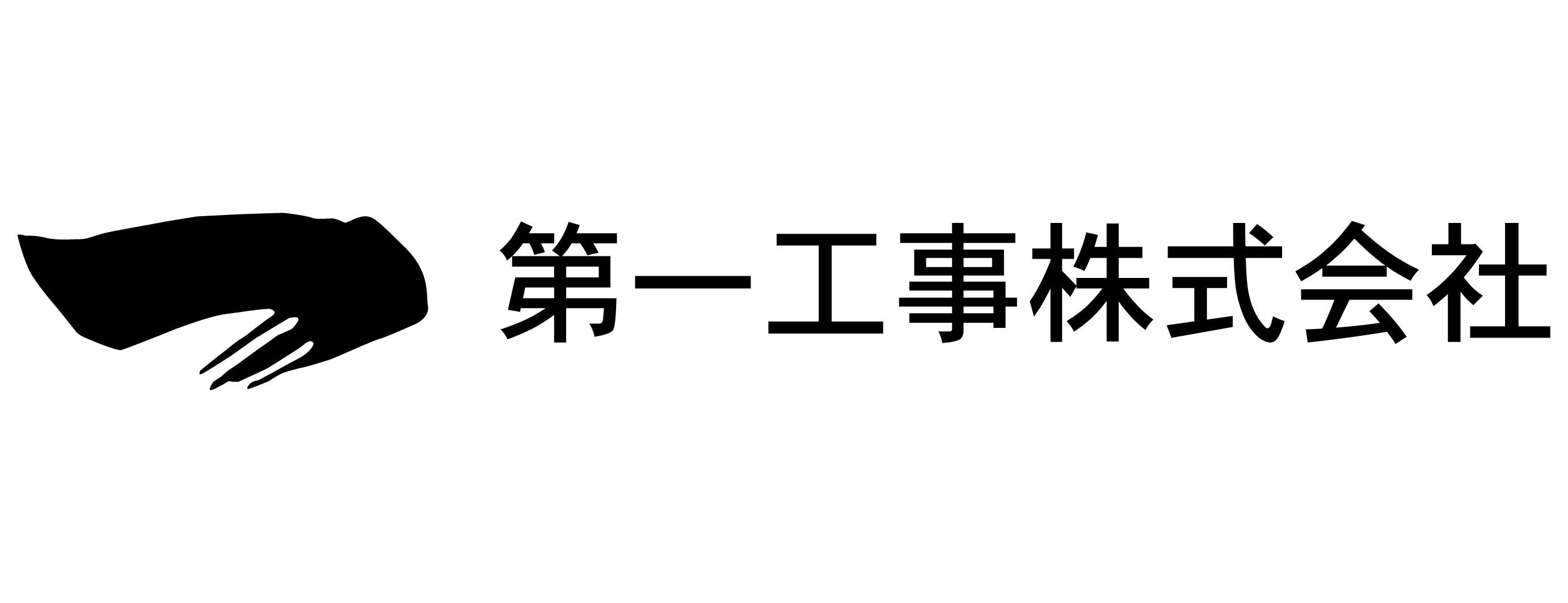








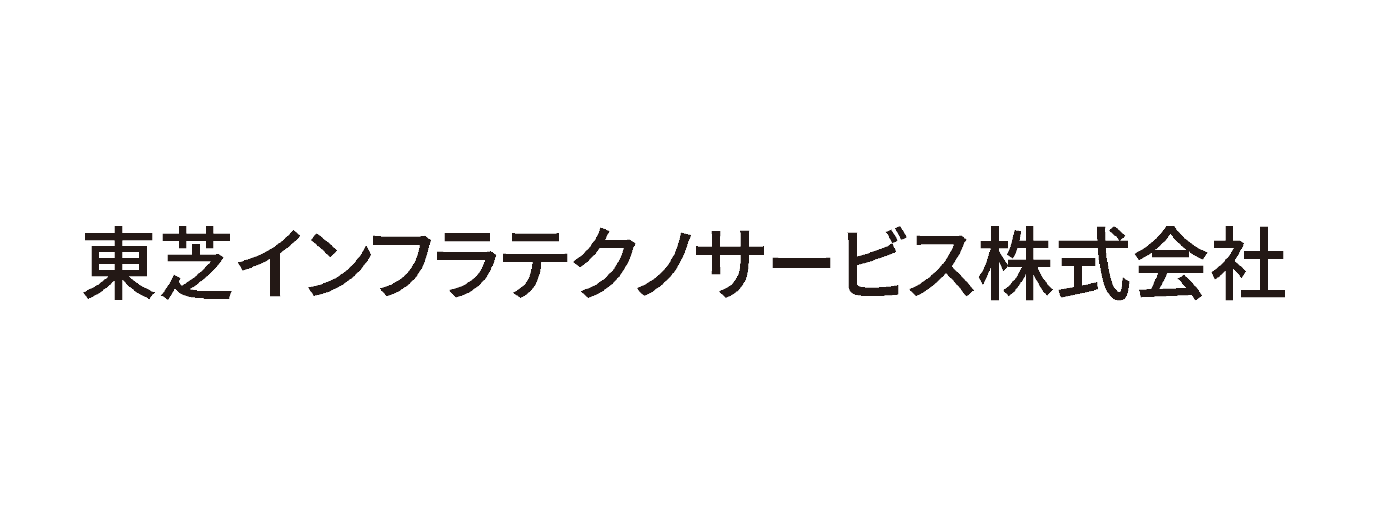










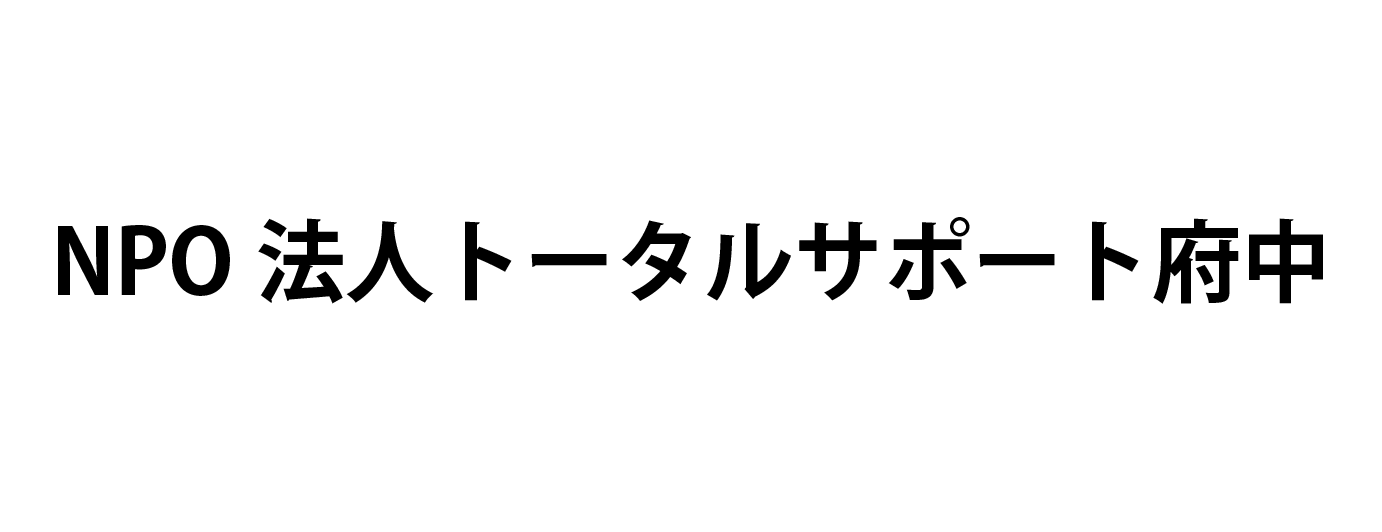


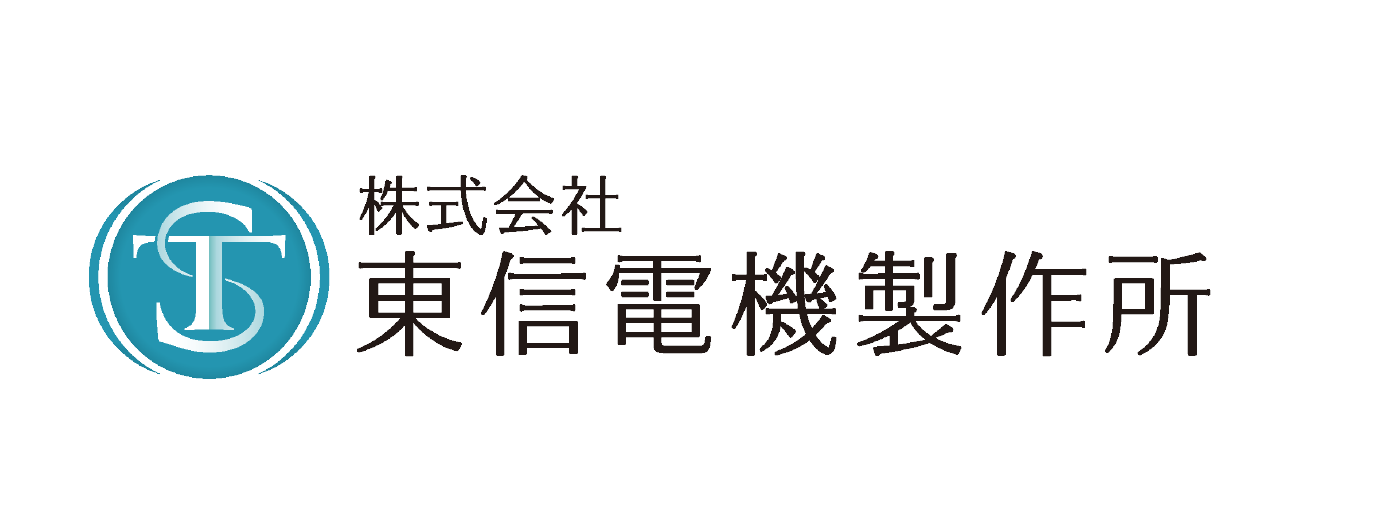


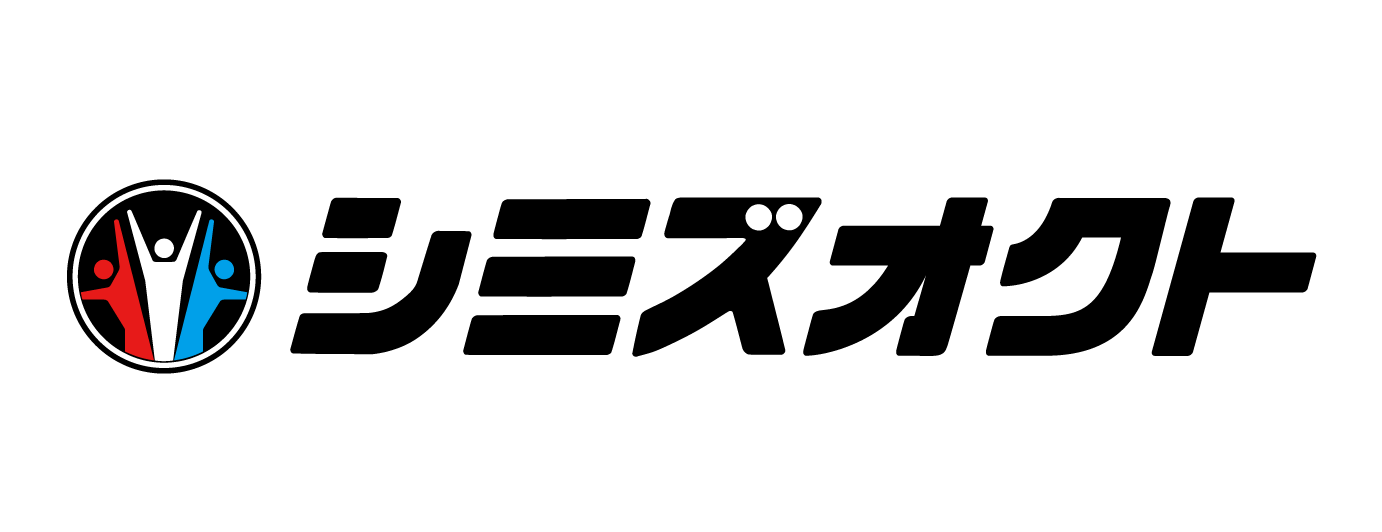






















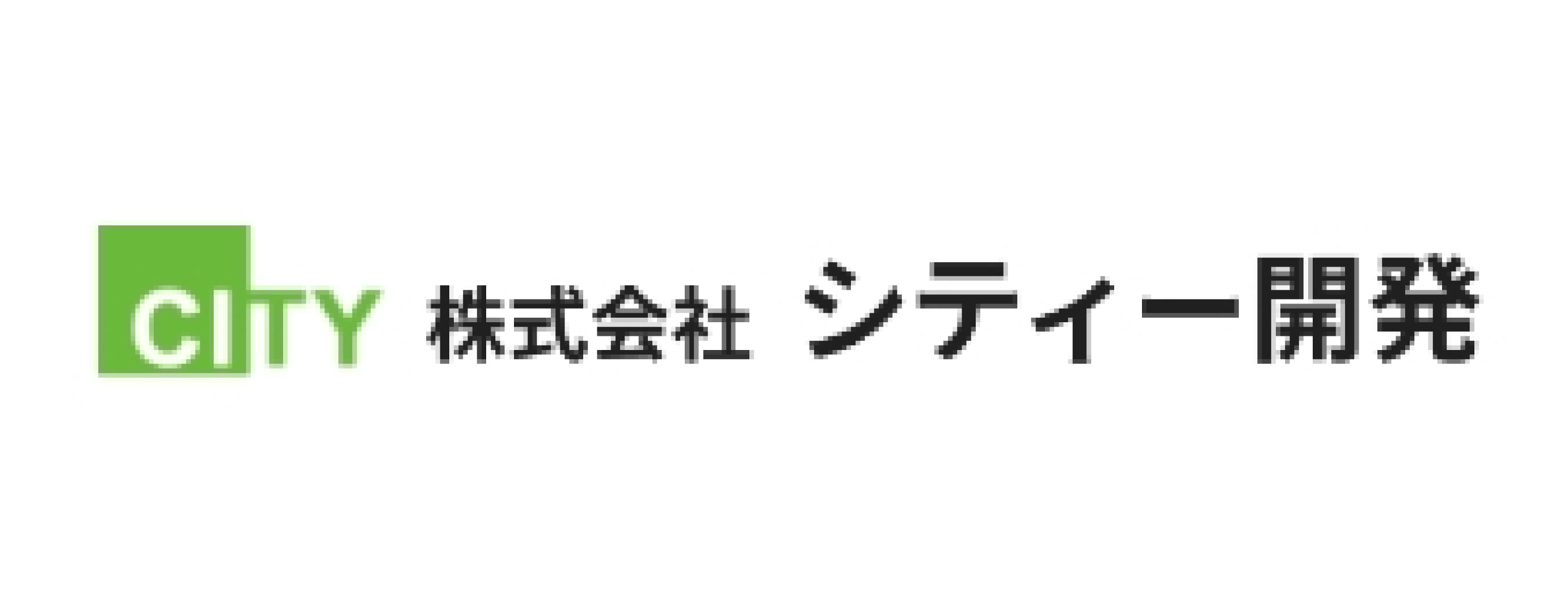



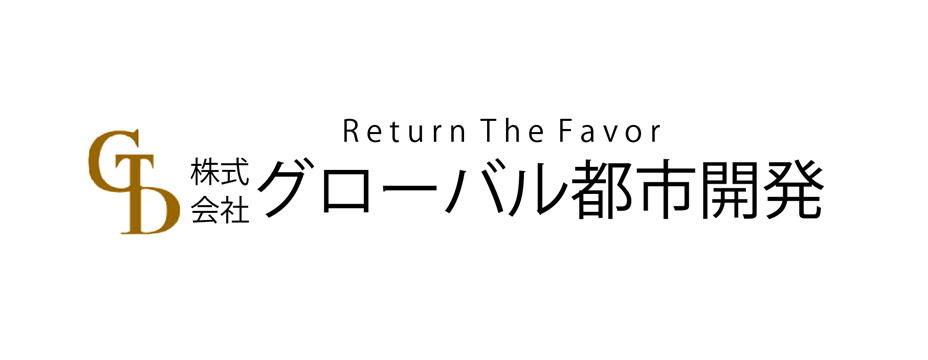
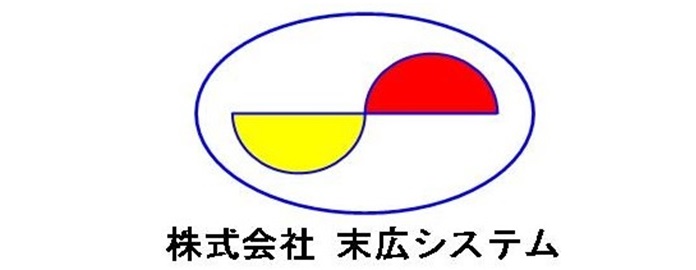


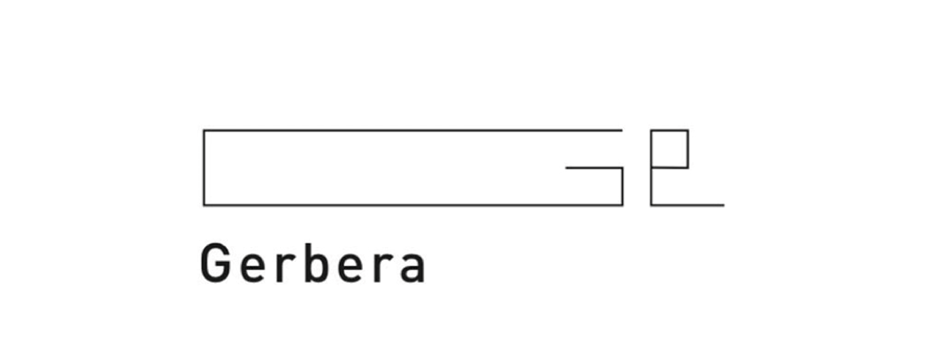

-02-コピー.png)






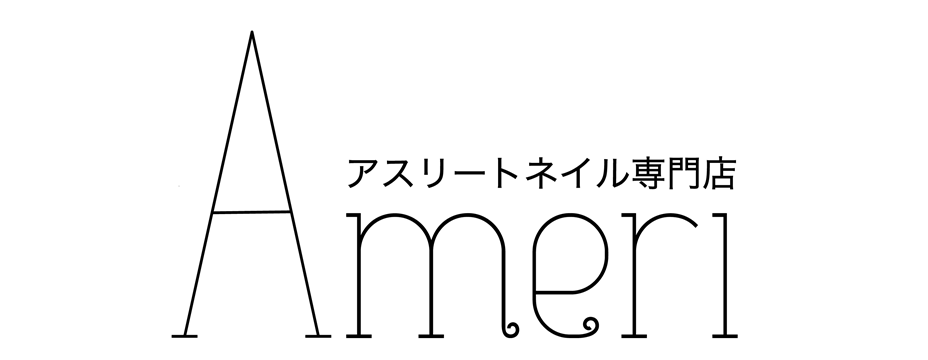


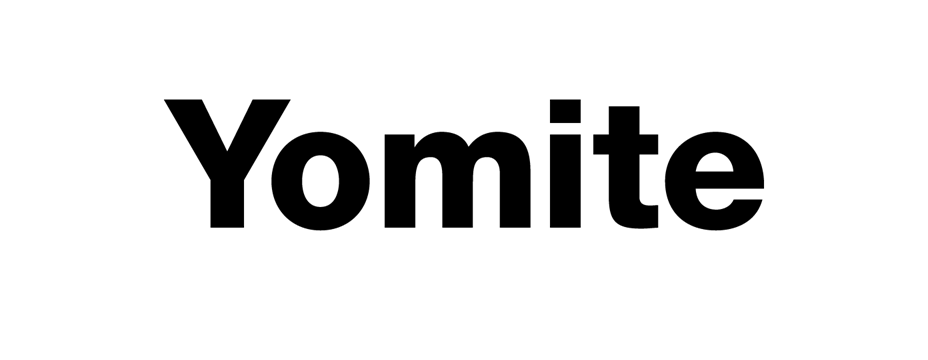




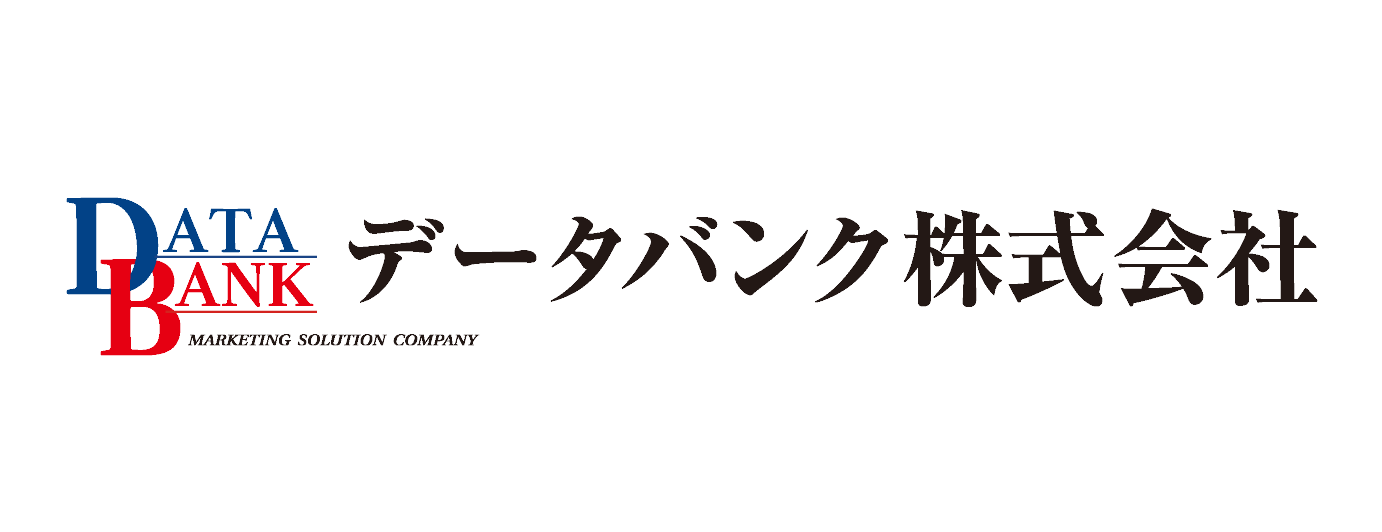



-1.png)






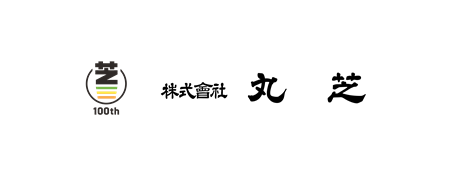

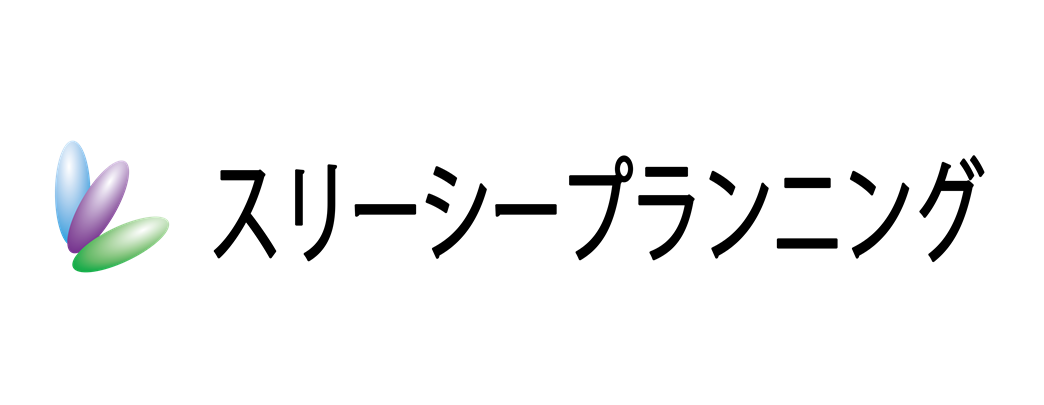





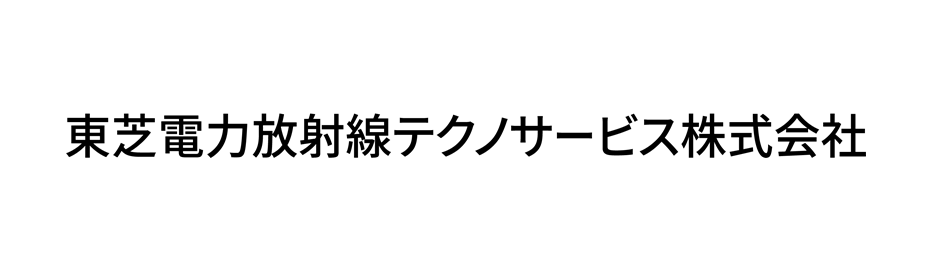









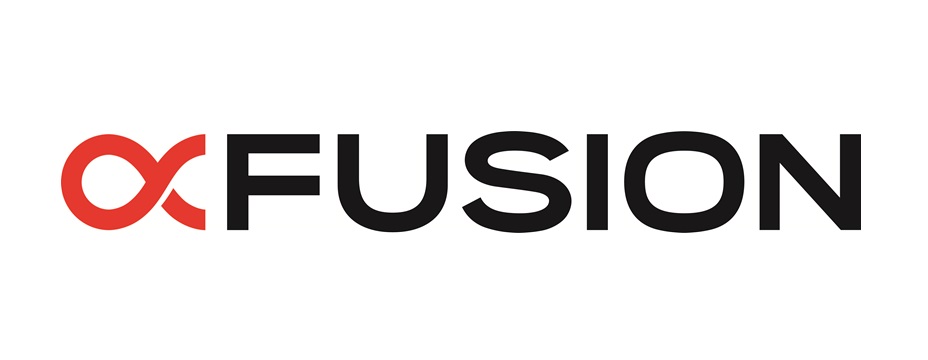












.png)
HP-logo.png)





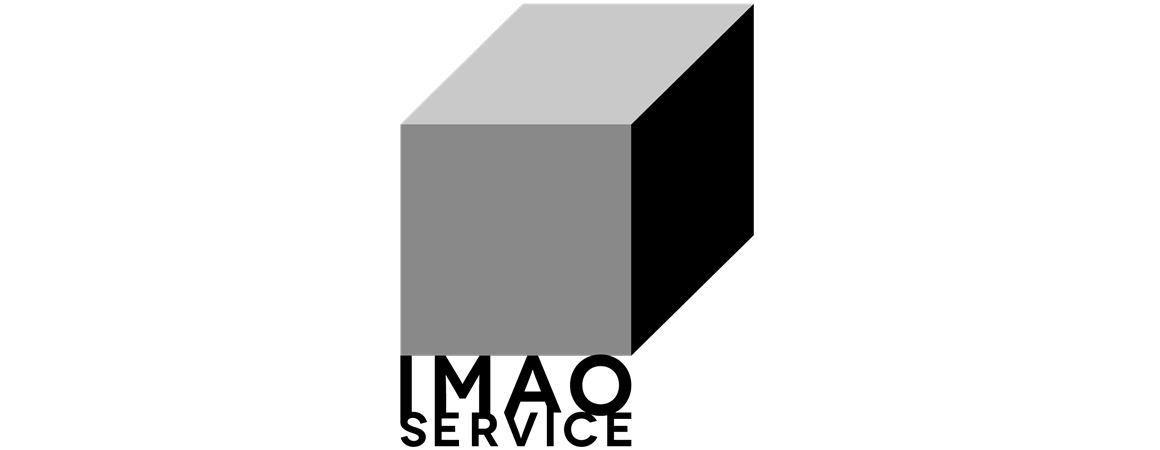

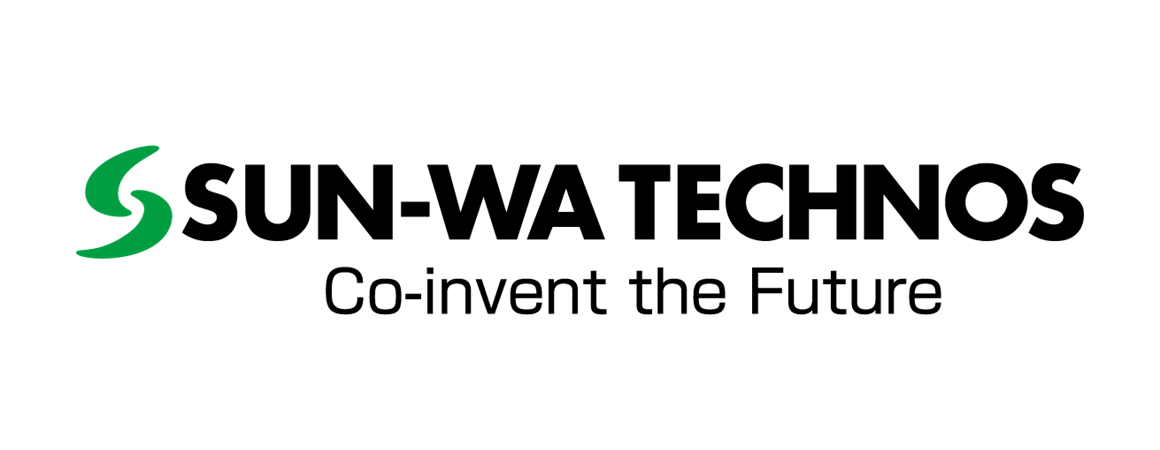
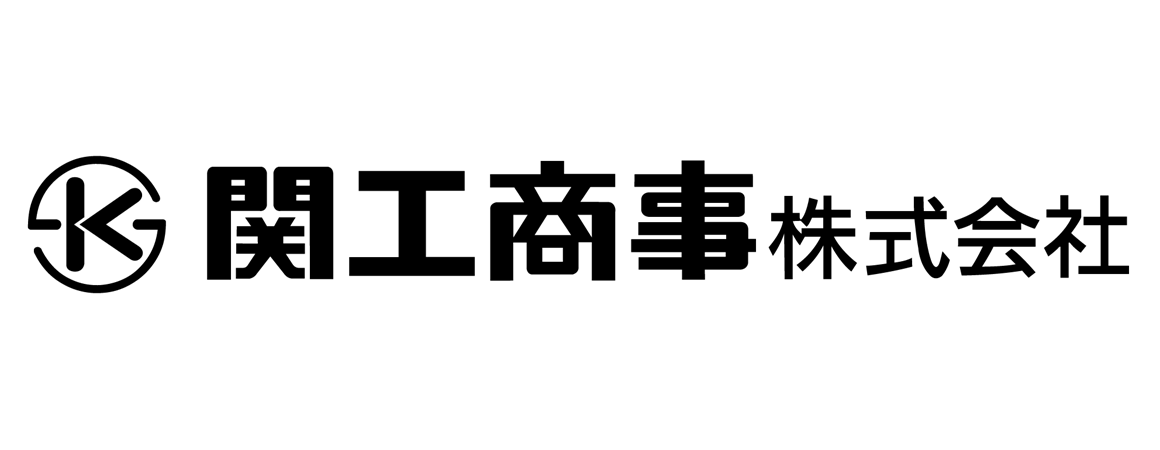
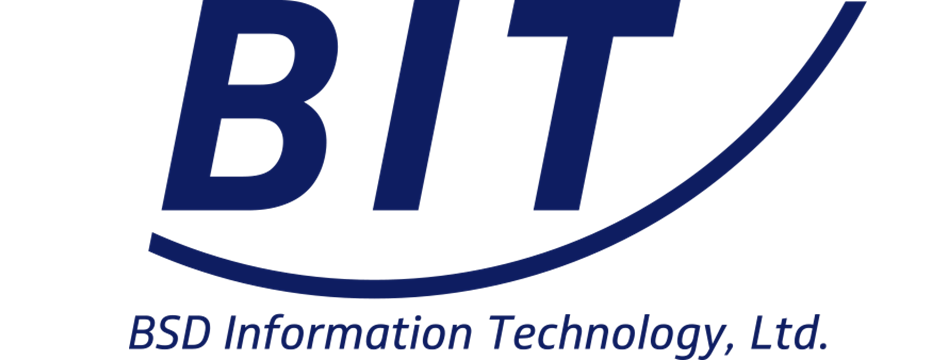




-復元.png)