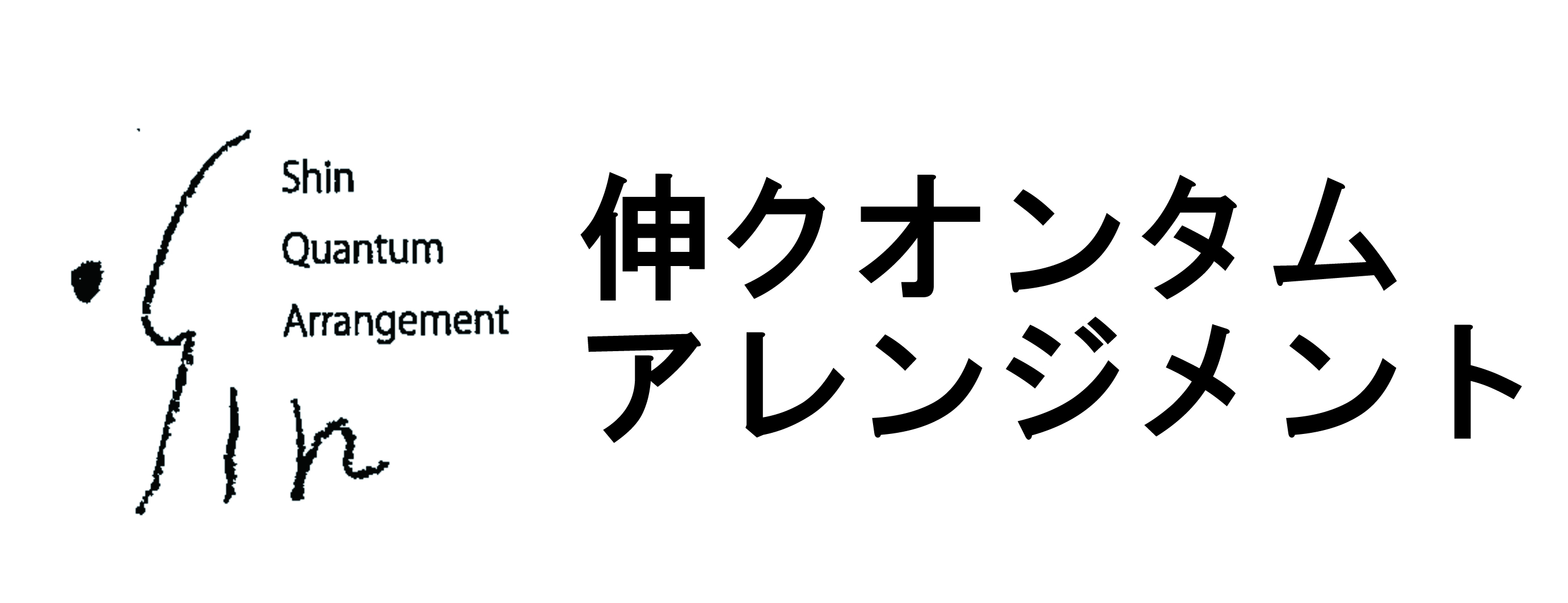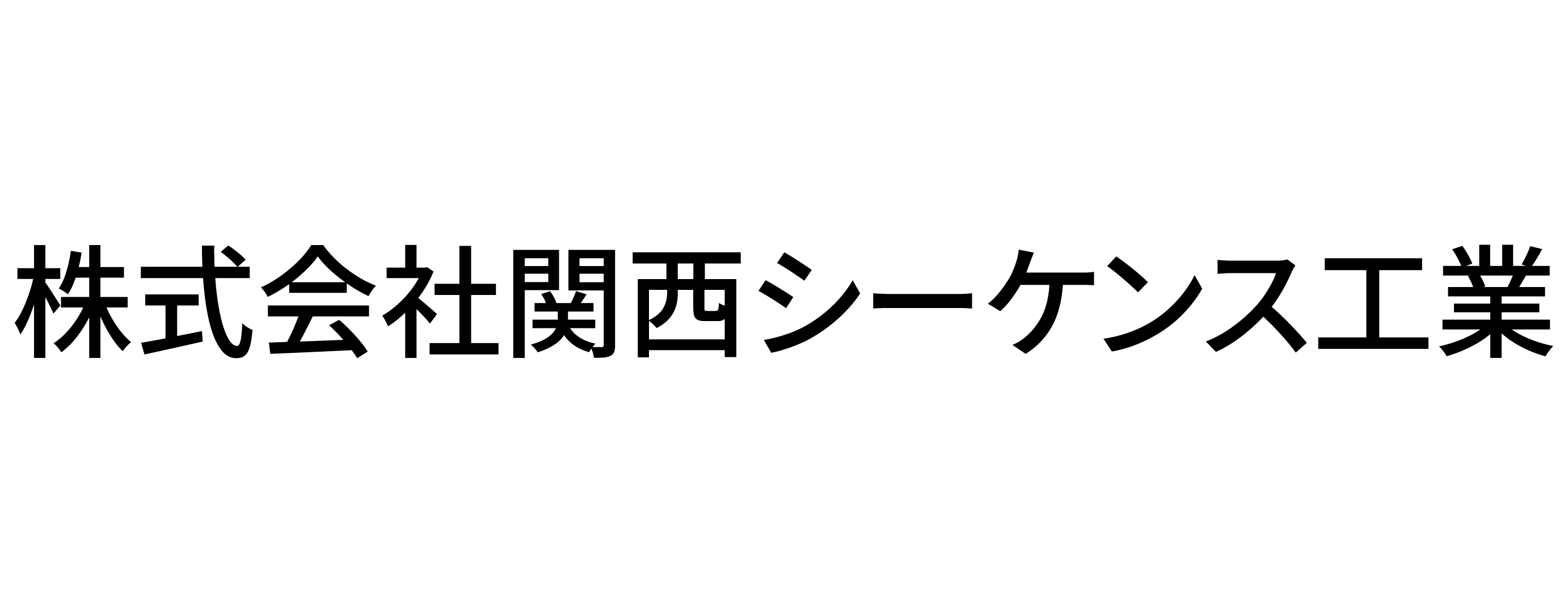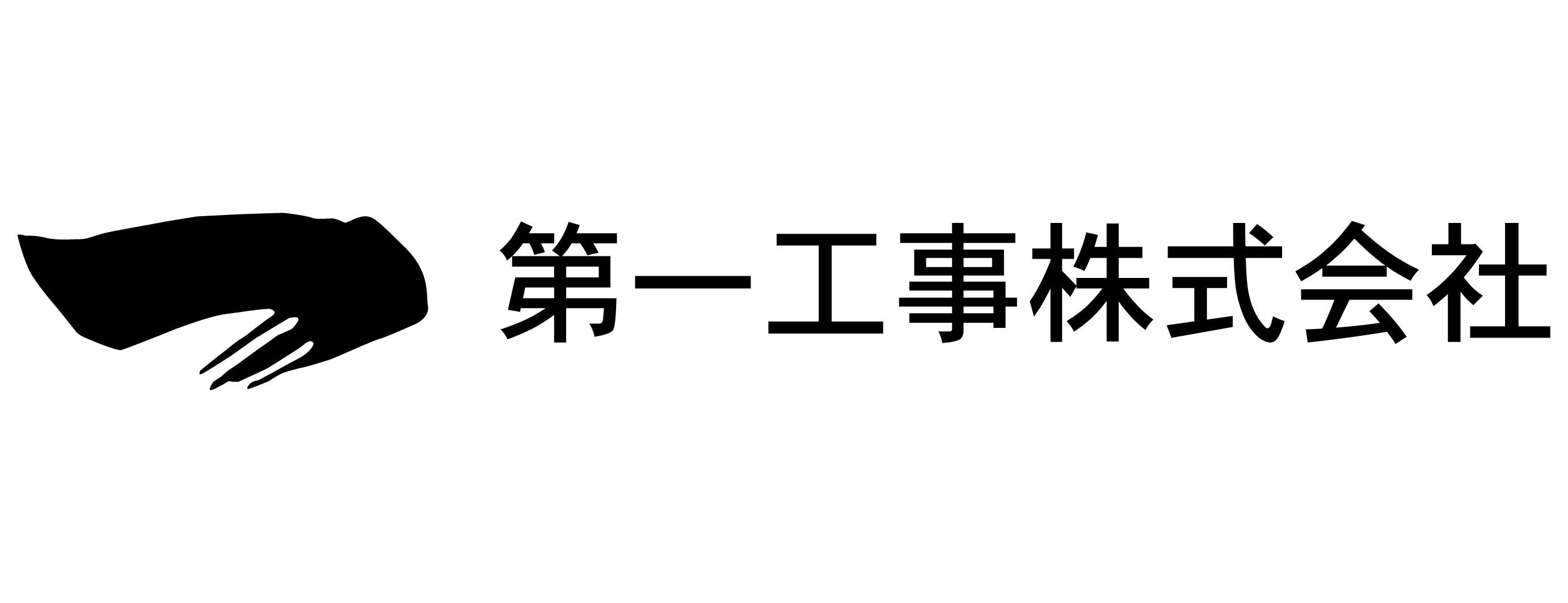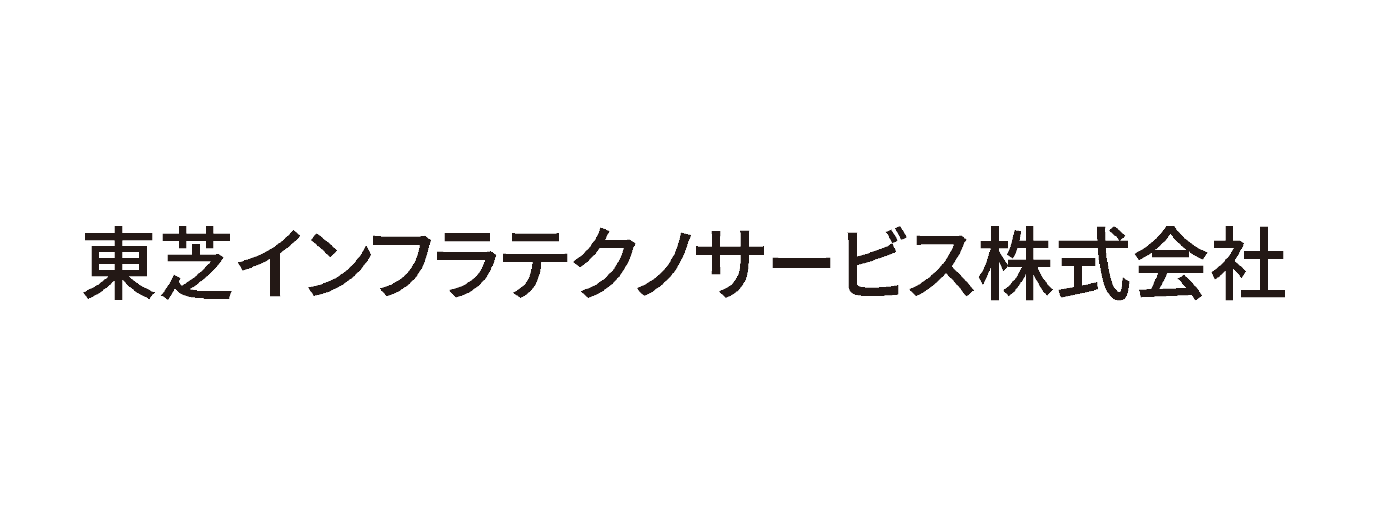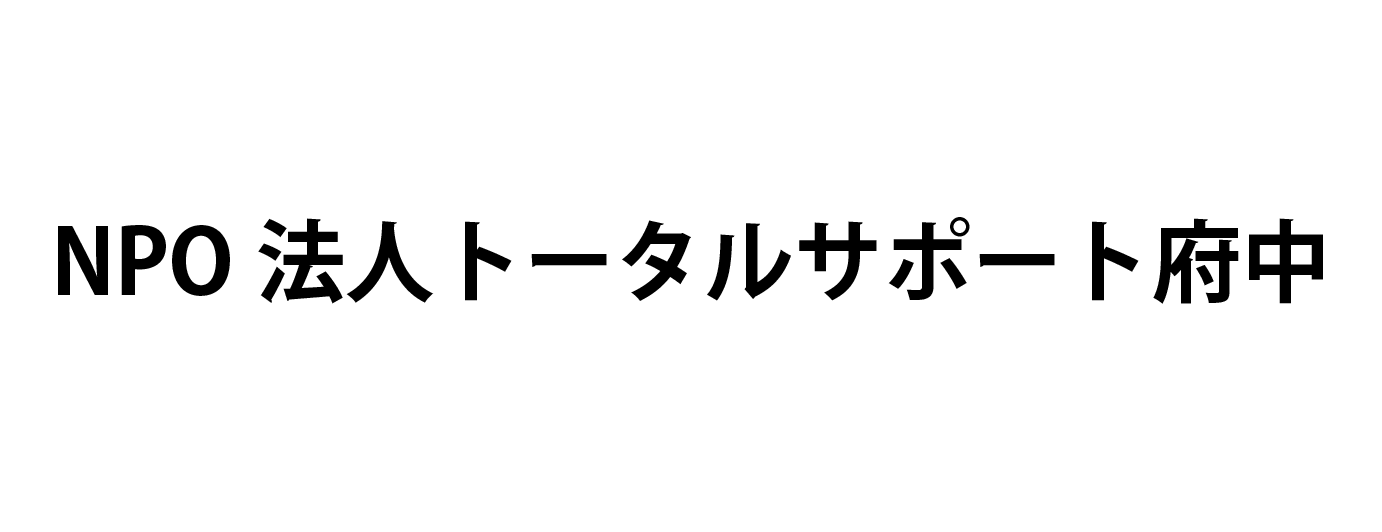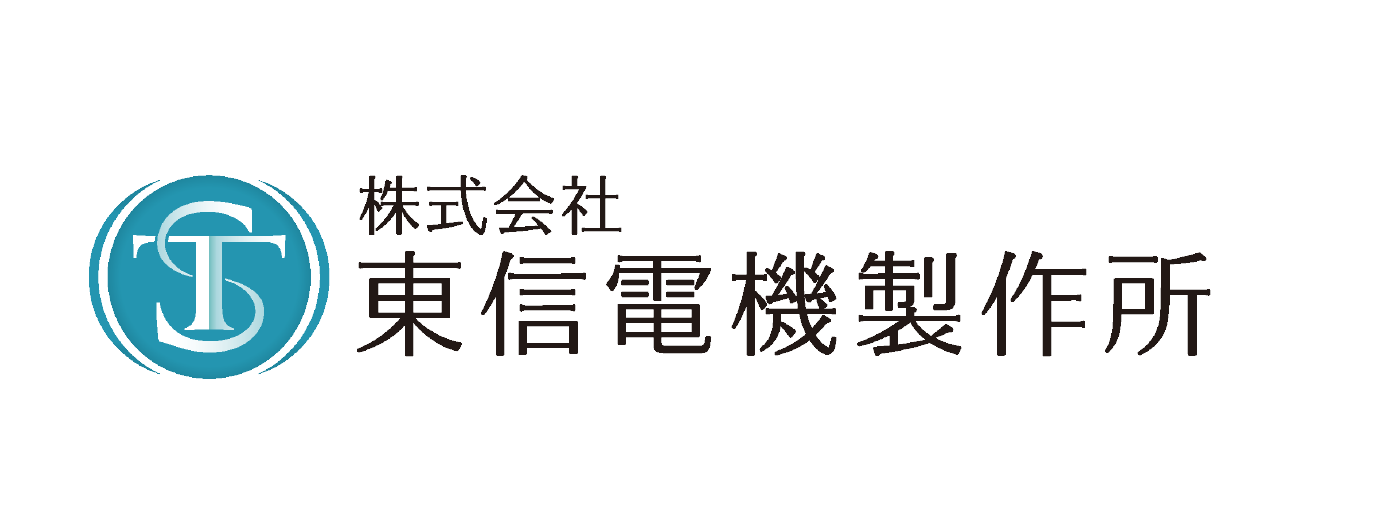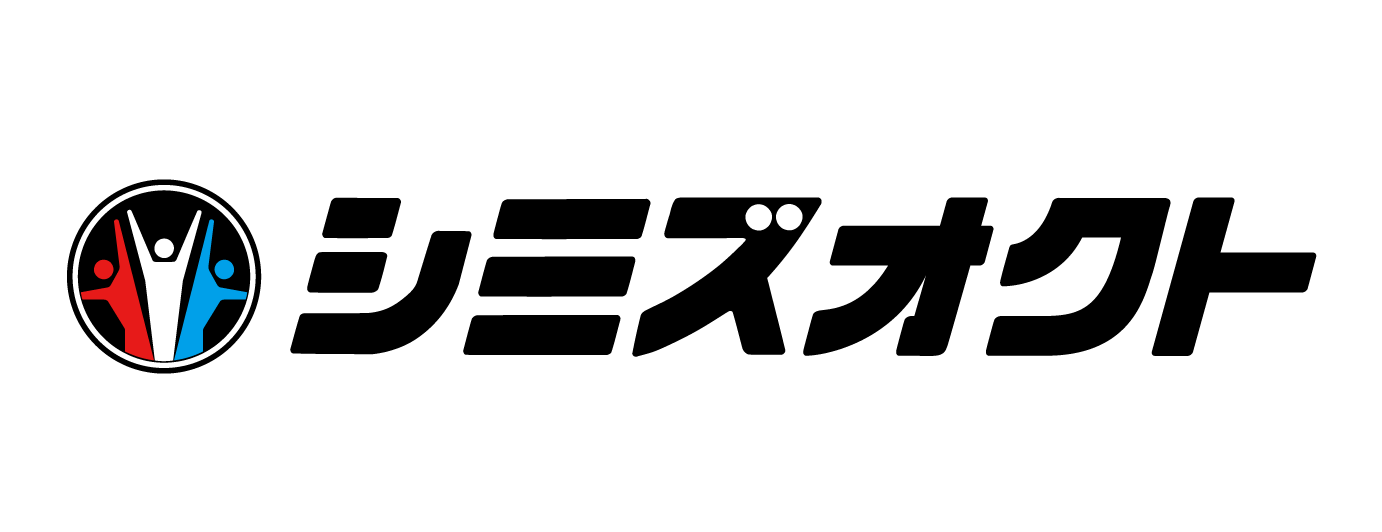【物語りVol.49】 SH ジャック・ストラトン

5歳でラグビーを始めた。父も、祖父も、叔父も、ラグビーをやっていた。地元のクラブで楕円球を追いかけることは、ジャック・ストラトンにとってあらかじめ日常に組み込まれていたものだったかもしれない。
「ニュージーランドの子どもたちがやるスポーツと言えば、やはりラグビーですからね。僕の実家は農家で、広大な土地のある田舎で育ちました。兄弟や親せきの子どもたちといつも外で遊んでいて、僕はとても負けず嫌いだったので、何をするにしても競争でした。弟とはどれだけ遠くまでボールを蹴ることができるか、競い合ったりしたものです」
ラグビーを続けていくなかで、プロ選手への憧れが募っていく。カクテル光線に照らされたスタジアムに立つ自分を、想像してみたりもした。
「プロでやりたい気持ちは、いつも心のどこかにありました。でも、本当にプロでやれるとは、思っていませんでした」
高校の最終学年を迎えたジャック少年は、ラグビーと進学を切り離して考えていた。学業優先へ傾いていたなかで、父から思いがけない提案を受ける。
「リンカーン大学というところへの進学を考えていたら、父が『ラグビーの奨学金を申し込んでみたら』と言うのです。その奨学金は、スーパーラグビーのクルセイダーズのアカデミーに関連づいたもので、高校生の僕は選抜チームにも選ばれたことのない選手でしたから、奨学金を申し込むことは自分にふさわしくないというか、とても恥ずかしい気持ちになりました。それに、奨学金を申し込むには、高校のコーチに必要な書類にサインをしてもらわなければいけない。それも恥ずかしいと思った理由でした」
自分の実力に似合わないことをしてしまうのでは、という控え目な思いが後ろめたさに似ていく。それでも、ジャックは勇気を振り絞って応募した。
「自分のテクニックやスキルを大学のコーチに見てもらい、それから4週間後に奨学金が認められました。あのとき申し込んでいなかったら、その後所属することになるクルセイダーズでもカンタベリーでも、東芝ブレイブルーパス東京でもプレーできていなかったでしょう。奨学金を提案してくれた父、書類にサインをしてくれたコーチには、ホントに感謝しないといけないですね」

大学卒業後は、カンタベリーでプロキャリアをスタートさせた。ストラトンにとって、新たな困難の始まりだった。
「プロ1年目は本当にタフなシーズンでした。まずはとにかく、チームに慣れなければいけない。それと同時に、学ぶべきことがたくさんありました。素晴らしい選手に囲まれた状況で、自信を持つのが難しい状況でした」
プロとしてやっていけないんじゃないか。このままずっと、試合に出られないんじゃないか──後ろ向きな気持ちが心を巣くう。
ここでまた、ストラトンは勇気を振り絞るのだ。自らを奮い立たせた。
「1年目のシーズンの最後に、クルセイダーズの選手と一緒にキャンプをする機会を得ました。とにかく自分のベストを尽くして、何を得られるのかを見極めようと考えました。そうすると、ニュージーランドのなかでもベストと言っていいクルセイダーズの選手と、戦えているなと感じることができました。強くてタフにいけている、テクニックもついてきていると感じて、気持ちよくプレーできたのです。その夏の間は、昨日の自分より成長できていると日々感じることができ、ラグビーキャリアのなかでも一番自信を得られる練習が続きました」

カンタベリーとワイカトを経て、18年にはクルセイダーズの一員となった。のちに東芝ブレイブルーパス東京でチームメイトとなるマット・トッド、セタ・タマニバルとともにプレーした。
東芝ブレイブルーパス東京には、20年シーズンに加入する。日本でプレーすることは、かねてから望んでいたものだった。
「父が学生のときにニュージーランド代表に選ばれ、日本で試合をしました。素晴らしい文化があり、楽しい時間を過ごしたと話してくれました。そういうこともあって、小さい頃から日本に特別な関心を抱いていたのかもしれません。高校時代には選択科目で日本語の授業を取っていましたし。エージェントを通じてオファーを受けたときは、すぐにチャレンジしようと思いました」
来日1年目の20年シーズンと21年シーズンは、主に10番でプレーした。3年目の22年シーズンからは、9番を主戦場としている。
「日本に来る前から、足が速くてスキルのあるスクラムハーフがいるのだろうな、と予想していました。実際に来てみると、ホントに素晴らしい選手が揃っています。すごく印象に残っているのは、東芝ブレイブルーパス東京でのデビュー戦です」
20年1月12日のトップリーグ第1節、サントリーサンゴリアスとの府中ダービーだった。ストラトンは10番を着けてスタートからピッチに立った。9番は小川高廣だった。
「スクラムからたかさんがショートサイドに持ち出して、60メートルぐらい走ったんです。秩父宮がすごい歓声に包まれました。日本人選手はすごいスキルを持っている、こういうプレーをするスクラムハーフはニュージーランドにはいないんじゃないかな、と思ったのを覚えています。いまはたかさんと同じポジションで、たかさん以外の日本人選手とも、ライバルとしてポジションを争っています。チーム内で競争があるのは、とてもいいことですね。成長できるチャンスですから」

2022-23シーズン序盤は、リザーブでの出場が続いた。K9と呼ばれるメンバー外も経験しているが、心が灰色に染まることはない。
「プロ1年目にクルセイダーズのキャンプに参加したときに、メンバー外でもどういうふうにすれば良くなれるのかを、学ぶことができました。試合に出ていなくてもチームに貢献できることを、確認することができたのです」
ウィズコロナの社会が少しずつ落ち着いてきたことで、オフザフィールドでもチームメイトと交流ができるようになってきた。日本人選手とゴルフに行くこともあり、中尾隼太が主催するタコ焼きパーティーも毎年の恒例イベントだ。
「ゴルフはたかさんと隼太さんは必ずいて、他の選手も来ます。タコ焼きパーティーは隼太さんが大阪出身のすぎさん(杉山優平)とタクローさん(松永拓朗)を呼んでくれて、僕が新加入の外国人選手を連れていって、交流を深めるというのを毎年やっています」
日本語の学習意欲は旺盛で、外国人選手では一番うまいと評判だ。日本語で抱負を語ってほしいと頼まれると、ストラトンはスタッフに「これで合ってる?」と確認してから言った。発音もイントネーションも完璧な日本語には、「どんな立場でもチームに貢献していく」との強い意志が込められていた。
「日本で一番のチームにしたい」
(文中敬称略)
(ライター:戸塚啓)

【連載企画】東芝ブレイブルーパス東京 「物語り」
・物語り一覧はこちら



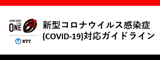



















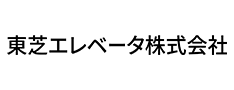



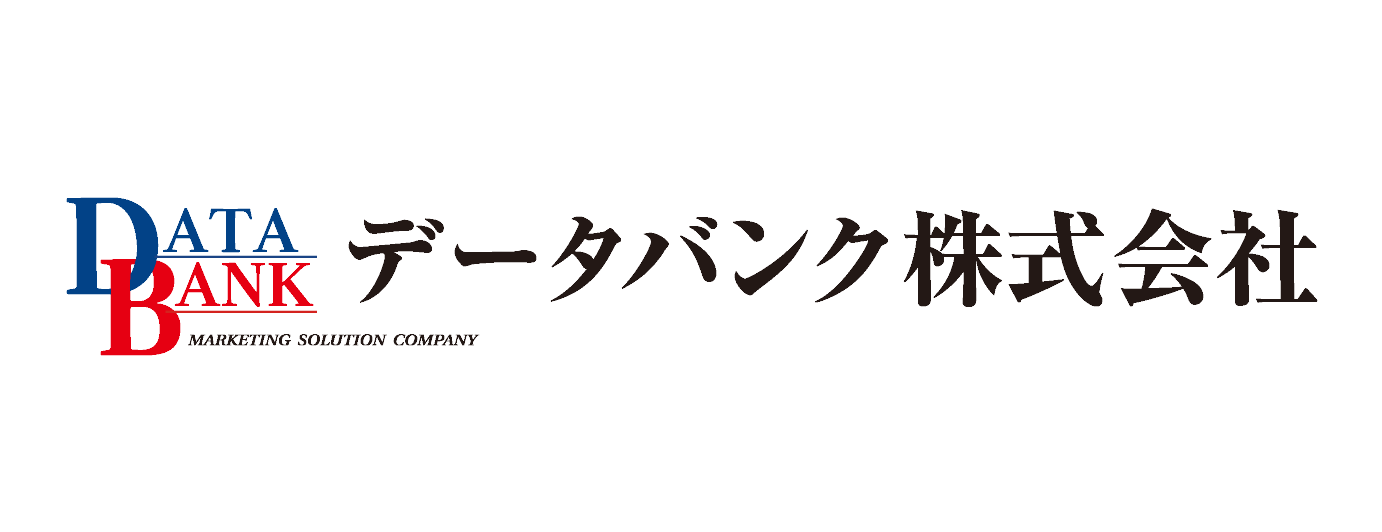


















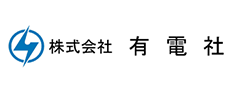


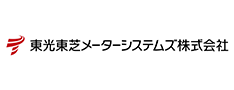
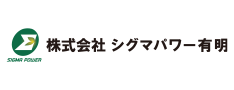

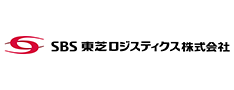




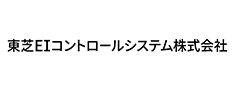

.jpg)



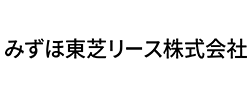
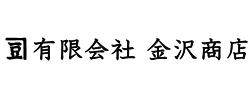
-07.jpg)


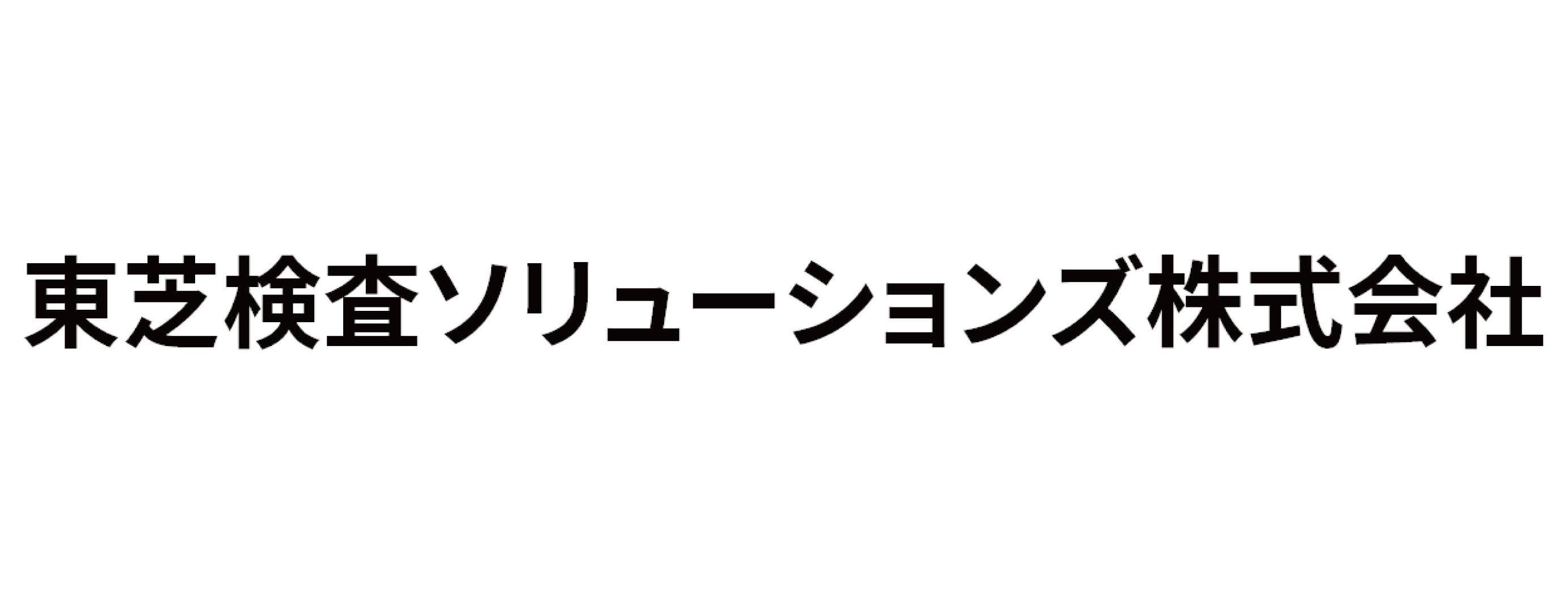





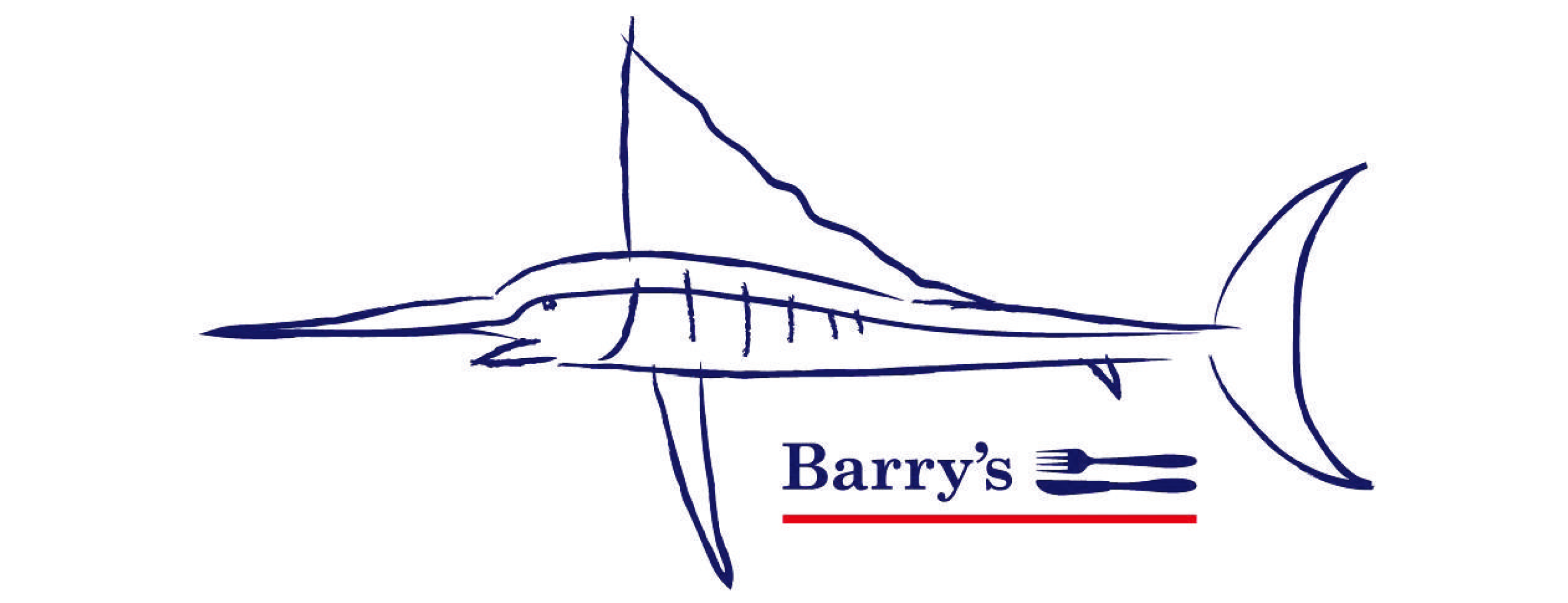

日本計装.jpg)